2025年5月歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」昼の部観劇記

令和七年(2025)五月二十三日(金)、梅雨入り前の貴重な晴天の中🌞、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」を昼夜通しで観劇してまいりました! 🎭🎉
八代目・菊五郎と六代目・菊之助の襲名披露公演の始まりとなる舞台です。わたくしミナミが直に見た歌舞伎座で思ったことやちょっと面白いなと感じた内容を紹介させていただきますね✨
なお、演目の詳しいあらすじなどの内容を解説するものではないことをご理解ください🙇
公演の詳しい内容については「歌舞伎美人」をご確認ください👇️
➡️ 令和7年5月「團菊祭五月大歌舞伎」
🟨 ゴレンジャー出陣!?『寿式三番叟』
まずは昼の部の幕開き、『寿式三番叟』からご紹介。
『三番叟』はさまざまなバリエーションがありますが、今回は「襲名を寿ぐめでたい舞」として、團菊祭の開幕にふさわしい厳かな儀式として始まりました。最初に登場するのは、中村又五郎の翁(おきな)に中村雀右衛門の千歳(せんざい)、中村米吉の附千歳(つけせんざい)という女形二人。そして少し離れた位置には、黒衣裳のの三番叟・尾上松也が現れます。
翁と千歳たちによる厳粛な舞が続き、まるで神事のような空気が舞台を包みます🌀。今回の團菊祭は、八代目・尾上菊五郎の襲名という歌舞伎界にとっての大事な節目。開幕にこのような古式ゆかしい儀式的舞踊を持ってくる構成に、見る側も心が正される気がしますね🧘♂️
やがて翁たちが退場し、松也の三番叟が一度花道へと下がると、舞台中央のセリから新たな三番叟、中村歌昇(紫)、尾上右近(黄)、中村種之助(緑)、中村萬太郎(青)の4人が舞台に登場、松也(黒)を含めた五色の三番叟が勢揃い🌈
ここから雰囲気が一転🎶。カラフルな五色の衣裳を身にまとった五人の若手花形三番叟達がまさに縦横無尽に舞台上を駆け巡り、華麗に華やかに舞い踊ります✨実に見事☺️
厳粛な序盤から一転して、軽快かつ目にも鮮やかな舞が繰り広げられ、團菊祭と菊五郎の襲名披露の幕開けを告げるにふさわしい晴れやかな雰囲気に包まれる演目、それが寿式三番叟でした。
ちなみに、五色揃った姿はやっぱりゴレンジャーを思わせますね〜
カレー好きの右近が黄色なのもそこからだきっと😆🍛
🟪 令和の團菊タッグ炸裂!『勧進帳』
続いては『勧進帳』。令和の團菊、十三代目・市川團十郎と八代目・尾上菊五郎の初の揃い踏みに歌舞伎十八番きました🔥
言わずとしれた歌舞伎十八番『勧進帳』
今回は本家團十郎が弁慶で新菊五郎が富樫、義経を中村梅玉が勤めます。
團十郎と菊五郎のやりとりはさすがの迫力ですが、梅玉の落ち着いた物腰がさらに舞台の深みを増している気がします🌊
ただ、私の注目ポイントは四天王。緊張した場面なのですが、どうにも滑稽な感じもするのがいいんですよね〜☺️
今回は尾上松也、尾上右近、中村鷹之資、常陸坊海尊に市川男女蔵という布陣ですが、花道の出のところから面白い。先に現れた義経に一礼してからその横をちょこちょこ横歩きで通り過ぎる……それを四人続けてやっている姿がなんともかわいい😁
富樫と一触即発になると、四人がものすごい形相で富樫に詰め寄ろうとして、それを必死で弁慶が押し留める💥若い亀井、片岡、駿河だけでなく本来落ち着いたキャラのはずの常陸坊まで一緒になってるというか、なんか三人に引っ張られちゃって「し、しかたなく…😓」みたいな表情に見えてしまって、緊迫の場面だけどなんか笑えるんですよね〜ここは🥴
でも、過去の映像では十二代目團十郎の弁慶で、新三之助(現・團十郎、現・松緑、現・八代目菊五郎)が四天王のときが一番鬼気迫る迫力があったと記憶しております👀
また、今回気になったのは、後見として市川右團次が登場していた点。舞台中にはたぶん出ていないのだが、ラストの弁慶が飛び六方で引っ込む直前、黒御簾の手前に控えて登場し、幕が閉まるとさっと退場🕴️あれはどういう意味があるのか…🤔
あらためて勧進帳の過去の映像見ると、やはり後見は常にいるみたい。故・市川左團次の追善公演『毛抜』で、團十郎が同様に男女蔵の後見として登場していたこともあり、幕引き後に飛び六方で引っ込むときだけ?
まあ、とにもかくにも『勧進帳』は、令和の團菊が真っ向からぶつかり合う重厚な舞台でありました。
ちなみに”菊五郎”は弁慶をすることはないようですが、吉右衛門の血も継いでいる六代目・菊之助はいずれは弁慶も演じることになるのでしょうか? 私はきっといつかやると予想しております😎
🟫 お嬢にしびれる😍『三人吉三』
さて、お次は『三人吉三』です。本作の見どころといえば……何といってもマルルこと中村莟玉ですよ🎉✨
配役は”おとせ”。いつものようにお嬢吉三に川に突き落とされるという役どころですが、今回はまあ、なんと可愛らしいことよ😍
三階席からは川面に空いた穴がよく見えますが、その手前に一度降りてから穴の中へと消えていく…。この淀みない一連のムーブはまさにマルルならでは(笑)
まあ、半分冗談はさておき、一番の見どころであるお嬢吉三(中村時蔵)の名台詞、「月は朧に…」これを聞いた途端しびれましたね〜🌕🎤
右近くんのお嬢で見たときはちょっとイマイチかなと。玉三郎丈の映像でも、正直この人にはあんまり合わないかな〜だって”女性の役”ではなく”女装した男”だしな〜と感じていましたが、時蔵はなかなかに聞かせるものがありました🧐
これまで個人的に最も印象的だったのは福助さんです。コクーン歌舞伎のDVDで見たんだと思いますが、その台詞の迫力に「なるほど、歌右衛門を襲名という話になるわけだ」と納得させられたのを覚えています👏
さて話を戻して今回の三人吉三ですが——
お坊吉三を演じた坂東彦三郎は、時蔵のお嬢と好対照を成し、良いコンビに見えました👍 そして二人の掛け合いの中に割って入るのが和尚吉三の中村錦之助さんなんですが…やや存在感が薄い🫥
お嬢・お坊よりも格上でやり手の風格がほしいところなんですけどね〜どうも人の良さが災いしているのか、中間管理職の悲哀みたいな役柄に見えることが多いような😅
🎯最後に「三人吉三」観劇上のアドバイスとして、三階B席はよくないですね⚠️ お嬢の台詞のときに浮き上がってくる”朧月🌗”が見えません。一番前なら少しは見えてるのかもしれませんが、一番上の席ではまったく見えないのでご注意を🙂↕️
🟧 三人道成寺で親子共演💫玉三郎も舞う
さあ、昼の部の最後を飾るのは『三人道成寺』。丑之助改め六代目・尾上菊之助のデビュー演目ですが、共演は父・八代目と坂東玉三郎丈です💫
正直なところ、これまで『道成寺』という演目自体にそこまで強い印象はなかったのですが、今回の舞台は舞踊の魅力を存分に感じさせるものでした!😳
八代目はかつて玉三郎に「私が合わせるから好きなように踊りなさい」という旨のことを言われたそうだが、今度は自らの息子・菊之助に対して同じ思いなのだろうか。そして菊之助は子供ながらに女心をその舞踊でしっかりと演じており、その様子を見守るように舞い踊る玉三郎…🩰👀
三位一体ではない。そこにはそれぞれの立場で舞い踊る白拍子の姿がありました。
いやいや、前評判の高さは知っていましたが、これほどとは。これだけで見に来たかいがあったというものです😌💮
玉三郎にとっては、菊五郎や菊之助が血縁でないながらも、深い芸の繋がりをもつ“継承の相手”として見つめる姿勢があったのかな〜これは夜の口上においても感じたことですがそれは後ほど☝️
そして本作で意外な発見。多数登場する所化(坊主)たちの人数が、筋書にある27人に対して、舞台上には26人しか確認できない。あれ、誰か休演してる?🤨
と思いきや、よくよく筋書きを見てみると、金の烏帽子を渡す妙念坊の権十郎さんは並んでいない。あの役は特別扱いなのか。
ちなみに坊主の一人(玉太郎?)が披露した「米」のダジャレの最後、「どこへ消えたか備蓄マイ🍚」は客席でかなりウケてました😂
というところで團菊祭五月大歌舞伎昼の部は終わり、夜の部へと続きますがそれはまた次回☺️🌙
※本記事内の写真は、すべて劇場にて撮影許可のあった場面、または私的鑑賞記録として撮影したものです。

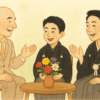








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません