キャンベル氏が照らした“菊五郎という役者”──菊五郎・菊之助 鼎談を読む(前編)
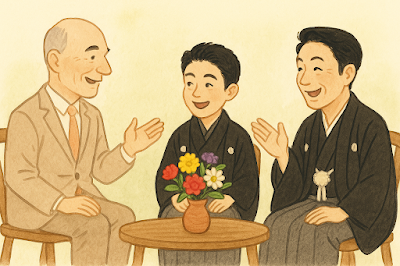
🎭 團菊祭に合わせた特別鼎談
令和七年 團菊祭五月大歌舞伎に合わせて、尾上菊五郎(八代目)・菊之助と日本文学研究者・ロバート・キャンベル氏との鼎談が行われました。
これを読むと、キャンベル氏のインタビュアーとしての能力の高さがよくわかります。そして、キャンベル氏によって引き出された内容の中から私が「これは……」と感じた部分を紹介しますね。
今回は前編ですが、来月後編が掲載されるようです。鼎談全文(前編)は以下のリンクから歌舞伎美人のサイトでご覧ください。
💡 インタビューの入り口
インタビューの冒頭、キャンベル氏がこう切り出します:
「実はお母様には一度お会いしたことがありまして。(中略)…それが絶妙なタイミングで、大人とはこういうものだと感じ入りました。」
🎤 スムーズなインタビューのためには、相手の気持ちをしっかり掴んで心を開いてもらうのが定石です。普通は本人のことを持ち上げることが多いのでしょうが、ここでキャンベル氏は、菊五郎の“お母様”との個人的なエピソードからさりげなく敬意を示しています。
一般的に日本人は、自分自身が褒められるよりも身内が褒められる方を喜びますが、欧米ではそれほどでもないと聞きます。アメリカ出身でありながら数十年日本に暮らすキャンベル氏は、日本人以上に日本の文化に精通していることが伺えますね。
そしてこの“お母様”は、もう一人の鼎談の相手・菊之助にとっては“祖母”。つまりキャンベル氏は、一つのエピソードで親子二代の心を同時につかみにいっているわけです。
それに対して菊五郎が返した言葉は……
「一気に親近感が湧きました(笑)」
これはもう、ガッチリ心を掴まれてしまったようです😄
さらに、キャンベル氏は自分の立場を説明しながら、直近で観た菊五郎の舞台を絶妙に褒めます。
それを受けて、菊五郎は日本人らしく謙遜で返す——いい流れができました。
そして話題は傍らにいる菊之助へ。話を振られての第一声は、
「わぁ!」
はい、持っていかれましたね(笑)
キャンベル氏、11歳の子どもの心をつかむことなど朝飯前といったところでしょうか。
🎐 弁天小僧と名跡の重み
ここから話題は、菊五郎家にとって特別な役である「弁天小僧」へと移っていきます。
菊五郎が「鏡獅子」についてもちょっと興味深いことを話しますが、キャンベル氏はどうやら「弁天小僧」について聞きたいようで、話をそちらに振っていきます。
この流れで、菊五郎と菊之助がそれぞれの思いを語ります。
そして、五代目、六代目、七代目……と続く「菊五郎」という名跡の重みについて、菊五郎が語り始めます。
📝ここがこの鼎談で私が"一番のポイント"と感じたところです。
「今の時代に歌舞伎がどうしたら生きた演劇であり続けるのか、と考えていくと、先人たちの功績も冷静に捉えることができ、『歌舞伎とともに生きる』ということが大事なのではないかと思います。代々の菊五郎もそうやってその時代時代を『生きて』きたのではないかと。」
それに対してキャンベル氏が返します。
「今を生きる歌舞伎俳優として、菊五郎さんは今の時代をどのように見ているのか伺いたくなりました。」
菊五郎の答えは、今この時代にこそ歌舞伎が必要であるという確信に満ちたものでした。
「ある意味、個の時代だと感じています。世界的に見ても、力の強いものが勝ち残っていくような。でも歌舞伎の古典は、忠義や義理人情、人との繋がりを大事にしていて、人を慮る心を芯に置いています。古典は難しいという先入観があるかもしれませんが、生きやすくなるヒントが沢山詰まっている。今こそぜひ、現代の皆さんに触れていただきたいですね。」
🎯この言葉に触れたとき、私は「ナウシカ歌舞伎」を思い出しました。
菊五郎が描くテーマと、ナウシカの世界観が一致したからこそ、「歌舞伎にする意味がある」と判断したのではないかと、今さらながら腑に落ちました。
🤝 團十郎との絆
続いて、キャンベル氏が注目したのは「勧進帳」。
團菊祭でもうひとりの主役である團十郎とのやり取りに期待を寄せます。
その話を受けて菊五郎が語ったのが、2つ目のポイント。
「團十郎さんには『(襲名披露演目の)道成寺の前に大丈夫?』と心配されましたが(笑)」
そこには、共に時代を背負ってきた者同士のシンパシーと、
だが、お前には負けないという確固たるプライド……そんな気がします。
つい先日のテレビ番組で稽古場での團十郎(弁慶)と菊五郎(富樫)のやりとりを短い時間ですが見ることができましたが、稽古にも関わらず、そのやり取りの迫力……そして傍らで見守る尾上松也の真剣な眼差しが、その緊張感を物語っているようでとても印象的でした。
💃 玉三郎との思い出
道成寺といえば、菊五郎と玉三郎の「二人道成寺」。
キャンベル氏もその思い出を語りながら、話はそちらへと移っていきます。
その中で菊五郎が明かしたのが、3つ目のポイント。
「(玉三郎の)お兄さんは『あなたは好きに踊りなさい。私が合わせるから。先輩と後輩というのはそういうものなんだよ』と言ってくださったんです。」
これは想像ですが、当時の菊之助はこの言葉を聞く前にかなり厳しいことを言われ続けていたはずです。
実際にテレビ番組などでも、立役の中村虎之介が何度もダメ出しを受ける姿や、
女方の中村米吉が「あなたは歌舞伎の家に生まれただけだね」と辛辣な言葉をかけられたことを語っています。
にも関わらず、「私が合わせるから」という言葉を言わせたということは、
玉三郎はなんらかの意味で八代目・菊五郎を認めたということではないでしょうか?
そして、その話を聞いて目を輝かせながら「頑張ります!」と語る菊之助の姿で鼎談・前半は締めくくられました。
✨ まとめと私見
ミナミの私見として、今回の鼎談・前半でキャンベル氏が見事に引き出したポイントは以下の3つです:
1.現在の菊五郎が目指す歌舞伎
2.菊五郎と團十郎の見えない深い絆
3.玉三郎も認める八代目・菊五郎という役者
もちろん、ある程度の打ち合わせはあったかもしれません。
ですが、それを踏まえたとしても、キャンベル氏のインタビュー力と歌舞伎理解の深さがなければ、この内容は引き出せなかったと私は思います。
後半は6月に掲載予定とのこと。七代目・菊五郎の話が出てくるのではと予想します。
ただ、あの人の場合はいつも女の話ばかりしている印象があるので(笑)、
むしろその対比で八代目の実像が見えてくるかもしれません。キャンベル氏の続編にも期待大ですね!
📖 後編リンク
※六月に後編公開されました。以下よりご覧いただけます📖👇
※六月にミナミが書いた後編については以下よりご覧いただけます📚👇


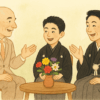








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません